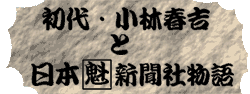
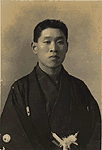
初代・小林春吉
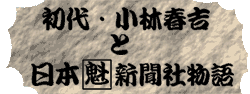
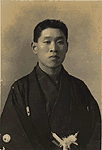
|
実父・小林春吉とは面識がない、と書いた方がいい。 話したこと、彼の手を握ったこと、一緒に飯を食べたことも、僕の脳裏の何処を探しても彼の記憶はカケラもない。 母・牧ふみの記憶では、僕が生まれた1944年(昭和19年)10月10日、彼は何らかの犯罪容疑で拘束されていた。僕が生まれて間もない1945年(昭和20年)1月、母は僕の顔を見せに春吉に面会した。 場所は「神奈川県鶴見刑務所面会室」と母は記憶していた。が、正確には「鶴見警察署の留置所」か、あるいは横浜・大岡山拘置所のことではないか、と思う。 面会に行ったのは、春吉から米粒で「会いたい」と書かれた”板製の手紙”が届いたからである。筆記用具を持たない牢獄の彼は、食事が支給されると米粒を一粒一粒残し、隠し持った板に張りつけて、手紙を作った。看守に「あとで金をやる」と”賄賂の約束”をして、母に”米粒の手紙”を届けさせた。 この時「警察に捕まった」とは知らされてはいたが、その後の消息を知らなかった母は彼が牢獄の中で「会いたい」と切望していることにはじめて気づいた。母もまた彼の子供が生まれたことを知らせたかった。 こうして、薄暗い”地下牢”で彼は息子「小林太郎」と初めて面談した。母の記憶では「可愛い」とか、「俺に似ている」といった言葉はいっさいなかった。そんな言葉を発する余裕は彼にはなかったようだ。 第二次世界大戦の末期、日本にも余裕がなかった。しばらくして、雪の降る2月22日、母のために春吉が借りていた千代田区豊島町のしもた家は空襲で消失した。そして3月9日から10日の東京大空襲。約30機のB29が東京を爆撃し、後の東京都記録では死者8万8793人。東京大空襲は、「骨なき墓」を山と築いた。 神奈川県の一部も火の海で、拘置所も火災に遭い、拘置している人間を解放するしかなかった。 小林春吉は大空襲の真っ只中、娑婆に舞い戻った。母は、と言えば、僕を背にアメリカ軍の空襲に逃げ惑っていた。 数日後、妻と息子に会いに春吉は母の実家、つまり「牧家」の疎開先・浦和市大田窪に現れた。彼は「一緒に住みたい」と申し出た。しかし牧家の人間は牢獄から出てきた男に「親子の再会」を許さなかった。その理由を母ふみは最後まで明かさなかったので不明である。 この時、父・春吉と息子の関係は途絶えた。 父・春吉が「日本魁新聞社」をつくり、新聞記者として華々しく活躍したことを僕が知ったのは、50年後の事だった。 |
|
僕が日本魁新聞社社長・小林春吉が精魂込めて書き記した「日本橋總覧」の復刻版を作ろうと思いたったのは、僕と父と母の複雑な関係に起因する。 母・牧ふみは1907年(明治40年)3月2日、東京都台東区柳橋一丁目で料亭「深川亭」を経営する牧文次郎の二男四女の末娘として生まれた。 僕が物心付く頃には、柳橋から2キロ離れた中央区浜町の宗教家、大木保之佑の後妻になっていた。大木保之佑は丸ハゲで愛嬌のある顔。あまり大きくもない土佐犬を飼っていた。 身延山系日蓮宗の熱心な信者で、彼を慕って集まってくる信者を集めてはお経を上げる。しかし、お布施は取ることもないボランティア活動で無収入に等しい。仕方なく、ふみは小さな駄菓子屋を営んで生計を立てていた。 「本当の父」と思っていた大木保之佑が病死したのは1952年(昭和27年)10月3日。僕は中央区立久松小学校の2年生だった。 母は仕方なく、駄菓子屋を畳んで柳橋の実家に戻り、すでに代が代わりし、姉・きみが経営する料亭・深川亭を仲居として手伝うようになった。姓は「大木」から「牧」に変わり、僕は台東区立育英小学校に転校した。 日大一高3年生の時、僕は早稲田大学第一政経学部新聞学科を受験した。当時、NHKテレビのドラマ「事件記者」が人気で、僕は新聞記者に憧れていた。当時、新聞記者になるには早稲田を卒業するのが早道、と言われていた。 幸い合格。入学手続きに必要な戸籍謄本を台東区役所に取りに行った。この時、僕は初めて「大木保之佑の子供」ではなく「小林春吉の子供」と知った。愕然とした。 戸籍にある「父・小林春吉、母・牧ふみ 男・太郎」という記載。これは父と母が結婚せずに子供が生まれた、ということを意味していた。「長男」「次男」と書かれるべき箇所が「男」となっている。私生児だが、小林春吉という人物が「我が子」として認知したという証明である。 戸籍を手がかりに、僕は実父・小林春吉がそのころ中央区内に住んでいることを突き止め、その日のうちに「小林」という表札が掛かった家を探しあてた。 二階建ての木造のしもた家だった。玄関の格子戸が開いていて、土間の向こうに、人の足の裏が道路から見える。誰かが、ごろりと昼寝でもしているのだろう。男のしっかりした骨太の脚だった。僕は、この太い脚、ごつい足の裏が父親のもの、と直感した。 何度か「玄関に入ろう」と思った。顔を確認したかった。が、それがどうしても出来なかった。18歳の僕は、実子を捨てた人間をとても許せなかった。 その夜、僕は泣く母に「小林さんは、何をしていた人?」と聞いた。職業のことを聞けば、人間の輪郭が分かるような気がした。 母は「新聞記者よ」とそっけなく答えた。 |
|
大学を卒業して毎日新聞社に入社した後、「父親」のことを思い出すことはほとんどなかった。希望通り、新聞記者という職業に就いたのは因縁、というしかない。しかし、新聞記者の先輩でもあった父のことは努めて考えないようにしていた。 自分に子供が生まれた時も、チラッと彼に知らせようか、とも思ったがすぐ現実の繁事にとりまぎれた。無意識に、実の父を無視して生きていきたい、と思っていた。 47歳の時、僕は脳卒中で倒れた。 サンデー毎日の編集長として、睡眠時間3、4時間でモーレツに働いていた頃だった。過労。健康に対する過信だった。 三日三晩意識不明。生死の境をさ迷ってから、僕はなぜか実の父親に会いたくなった。これは渇きに似た感情だった。 理由ははっきりしない。ただ、会って父親に何か言いたい。具体的に何を言いたいのか分からないが、人生最大のピンチに、実の父親なら何か言ってくれるような、気がしてならない。 病院のベッドの上でのたうち回った。何度も何度も「父親に会いたい」という衝動に駆られた。どんな顔をしているのか。まだ、生きているのか。この渇望は募るばかりだった。 退院してから約一年。右半身マヒの僕は、杖を付いて父親探しを始めた。仕事の合間を見て、信頼できる友人の力を借り、父親探しを始めた。 中央区役所で小林春吉の「除籍謄本」を見せられた。彼は1972年(昭和47年)4月15日、東京都世田谷区で死亡していた。 彼の生年月日を見ると「1893年(明治26年)2月20日生まれ」。79歳で死亡していたことになる。 僕が生まれた時、彼は51歳だったことになる。 彼の除籍謄本を入手した1993年(平成5年)の秋から冬にかけて、僕は生前の父親がどんな人間だったのか、調べることに熱中した。 「血の繋がりがはっきりしないから、除籍謄本しか見せられない」と杓子定規に言う区役所に掛け合って、とりあえず戸籍謄本に「僕の姉」が記載されていることを知った。 小林蓮子さんである。彼女は僕の突然の連絡に驚き、面談した。 彼女は小林春吉と正妻・トメさんとの間に生まれた僕より19歳年上の姉であった。 彼女は戦争末期、つまり春吉が投獄されている頃、なぜか僕の母・牧ふみと同居していた。”父親の愛人”と同居し、腹違いの弟が生まれた現場に居合わせた彼女は、複雑な青春を送ったのだろう。 彼女には僕のおしめを取り替えた記憶まであった。 僕は小林蓮子さんの記憶を元に、すでにこの世にいない小林春吉の足跡を調べた。 以下は、母・牧ふみ、姉・小林蓮子さん、彼女の夫、小林良一さんらの証言、各種資料から分かった「小林春吉の一生」である。 |
|
小林春吉は1893年(明治26年)2月20日、父・小林幸三郎、母・小林古めの間に生まれる。 本籍は石川県鳳至郡島崎村字恋が浦カノ30番地。島崎村は現在の穴水町である。 この本籍は母・古めが生まれた所で、春吉が生まれた所は、その後、本籍地にした「北海道函館市鶴岡町32」と推測出来る。 明治の中頃、石川県から、かなりの数の人間が新天地・北海道に渡っている。春吉の親、幸三郎、古めの夫婦も開拓精神で函館に渡り、そこで春吉を生んだ、と思われる。 蓮子さんは、親戚の者から「幸三郎は警察官で函館署長を勤めたが、函館大火の責任 を取り辞職した」と聞かされている。が、函館には大火が何度もあり、一般的に「函館大火」と言われる1934年(昭和9年)3月21日の大火に関しては、僕が函館図書館の資料を調べた限り、その事実を証明する記述はない。 ただ、春吉が函館の警察官の家庭で青春を送ったことは事実で、16歳で上京する。 1906年(明治39年)のことである。 新聞配達や書生などをして生計を立て、彼は中央大学法学部に入学する。 彼は卒業と同時に新聞社に就職する。「都新聞社(現東京新聞社)に就職した」と小林良一さんは記憶している。 「都新聞は一個の小天地なり、世の中の重なる事柄は残らず其の紙面に備はれり」の主筆・黒岩涙香のキャッチコピーで有名な東京で発行された夕刊紙である。 現東京新聞には、当時の都新聞社の社員名簿は保存されていないらしく、それに加え、当時の新聞社の雇用体系は複雑で、正社員、契約記者、嘱託などが入り交じっており、春吉がどんな身分で、どんな分野を担当していた記者だったか判然としない。 ただ、都新聞は民間サービス業を中心にした読者が多く、彼はその後の足取りから、彼の取材対象は、銀行が建ち並ぶ室町、富沢町、大伝馬町、株屋が並ぶ兜町、薬屋が並ぶ、繊維の町・馬喰町、横山町、花柳界の矢の倉……といった日本橋界隈の「地域」ではないかと思う。 当時、日本橋は日本の中心街。春吉は日本橋界隈を走り回った。 |
|
小林春吉が大手新聞社「都新聞」を退社し、自ら「日本魁新聞」という新聞社を作ったのは1927年(昭和2年)5月、34歳の時である。 当時の日本の中心「日本橋界隈」に新聞記者として人脈が出来た彼は独立を考える。その理由は定かではないが、大新聞の組織の中で自分の意思を明確にすることは、なかなか難しかったのだろう。 応援者も出来、当時としては珍しい「民」からの情報発信に着手した。 彼は横山町・馬喰町新道(現・中央区馬喰町一丁目6)に事務所を借りた。大手総合衣料の「エトワール海渡」の本館、海渡ビル(現・日本橋クリニック)の前にある木造二階建てのビルの二階部分だった。 彼は「先駆け」(魁)という言葉が好きだった。 「魁」とは「衆に先立って敵中に攻め入ること」。転じて「物事のはじめになること」と理解していた。 同時に「官」の発想より「民」の発想を大事にしたい。 彼は自分の新聞社の社名に自由な発想を表す「魁」を使ったと思う、と良一さんは話している。 母と知り合った昭和17、8年頃まで、彼は「日本魁新聞」という1ページの新聞を週1回程度の間隔で印刷、販売していた。 社員は社長の小林春吉一人。記者も彼一人である。 娘の蓮子さんは、母トメさんと一緒に刷り上がった新聞を折り、町内に配達する手伝いをした記憶がある。 「新聞社」というが、全くの個人の情報言論機関、と考えればいいだろう。 春吉は正義感が強く、蓮子さんが通う小学校の教頭の不正を暴いた。あまり、家族のことなど考えない方で、蓮子さんは学校に行くと教職員からいじめられたこともあった。 記憶をたどるうちに、姉・蓮子さんは、彼が「日本橋總覧」というかなり厚い本を出版していたことを思い出した。 「おとうさんが一年がかりで書きあげた記憶がある」と言うのである。 僕は彼の自著「日本橋總覧」を探すことに着手した。 彼の考え方を知りたい。 「日本魁新聞」が存在しないとすれば、この本が、ジャーナリスト・小林春吉を知る唯一の資料になり得る。 「日本橋總覧」は容易に見つけることが出来た。中央区京橋図書館に保存されていたのである。 小林春吉が「日本橋總覧」を発刊したのは1939年(昭和14年)。第二次世界大戦が始まった年である。 日独伊の三国同盟。国民精神総動員委員会が創設され、軍事国家が泥沼の道を歩み始めた年である。 ところが、この本はむしろ軍部台頭に無関係で、江戸から昭和14年までの主として「民間」の歩みを整理しようとした書籍だった。 「5000頁は必要だったが、700頁以内にまとめなくてはならなかった」と彼が「小引」の中で書いているように、日本の最先端にある地域の歴史を最大漏らさず書き留めたい「意気込み」があったらしい。 写真、地図、資料も軍国色はむしろ薄い。劇場、料亭の類いの写真がかなり掲載されている。この年、警視庁は待合、料亭の閉店を通告しているぐらいだから、この本の編集方針は軍事下の時代に逆行している。 軍部独裁の世の中にありながら、商売に成功した人物を特集するユニークさである。 「民」の書籍である。 江戸時代の地図には珍しいものが幾つもあった。日本橋魚市の図、三井呉服店(現・三越)の図、文政12年大火焼場図……。 これは一流の資料と思えた時、僕はなぜか、ホッとする思いだった。 |
|
日本魁新聞社刊「日本橋總覧」を読み終えた僕は、資料としてこの本を復刻するこ
とが出来ないか、と思うようになった。
技術的な問題だが、復刻するには元本をバラバラにしなければならない。バラバラ
にするとなると、中央区京橋図書館にある元本を傷つけることになる。 復刻を決意してから「もう一冊、元本がこの世に存在しないか」と、僕は必死で捜 し出す努力をした。が、どうしても発見できない。 友人である出版社「港の人」代表、里舘勇治氏が杉並区高円寺北の古本屋「竹岡書 店」で「日本橋總覧」を発見したのは1998年の夏のことである。さすがに餅屋は餅 屋。彼に相談してから2ヶ月余りで、彼は父の本を捜し当てた。深く感謝しなくてはな らない。 竹岡書店では、この本に3万円の正札が付いていた。それなりの価値が認め られた書籍ということになる。これも僕を勇気づけた。 日本橋地域のシンボル、日本橋は1999年春、架橋八十八周年を迎えた。 何かの縁、と勝手に判断し、亡き父の「日本橋總覧」を記念すべき「日本橋架橋八十八周年」 の年に自費復刻することにした。 「し」と「ひ」を発音できない江戸っ子の僕には、ふるさと東京を愛する気持ちは 誰よりも強い。この本を復刻するのは、父とふるさとに対するプレゼントのように 思えてならなかった。 復刻費用は、オウム真理教告発キャンペーンを評価され1997年に日本記者クラ ブ賞を受賞した時の賞金50万円。それに98年中公新書で出版した「新聞記者で死に たい」の印税の一部を当てた。 300部。日本橋架橋八十八年のイベントに併せて自費出版した記念すべき「実父 の本」は、僕の友人と出版社、図書館に献本した。 さて、小林春吉は「日本橋總覧」を書いたあと、どう生きたのか。 「魁」が好きな彼は昭和10年代中頃、水洗トイレの販売を始めた。いかにも”先 駆け”の事業である。これも成功したようだが、その頃、経済犯で警察の厄介になった ことは始めに書いた。犯罪の内容については、依然として分からない。ただ、彼が母に 「厳密に言えば4人が追及されるべきものだったが、おれ一人ですめばいい」と言った ことがあった。従って、彼自身、犯罪の認識を持っていたことは事実である。 大空襲で牢獄から娑婆に出た彼は新橋第一ホテルを仮の宿とし、終戦と同時に銀座 七丁目で小林宝石店を開く。GHQの米兵が振り袖に興味を持つと知ると、地方の農家 から和服を買いあさり、米兵の持っているタバコやウイスキー、バターと物々交換して かなり儲けたらしい。 銀座タイムス社の銀座年鑑昭和三十年版に「日本料理・猩猩 小林春吉」という記 載が残っているが、彼は「小林宝石店」に続いて天ぷらやを中心にした小料理屋「猩猩」 を銀座七丁目「銀七小路」で始めた。さらに、江東区洲崎遊廓の前に「源氏の酒蔵」 を、銀座六丁目で「アルバイトサロン」を、と次々に時代にあった商売を始める。 「源氏の酒蔵」では、当時の日雇い労務者を相手にした「飲み放題」が話題になっ た。「雨が降る日はタダ」が大変な人気だった。雨が降ると「ニコヨン」と言われた労 務者は仕事にあぶれ、まったく収入がない。「源氏の酒蔵」は仁侠の店だった。 春吉はその頃(昭和33年)、野辺きくさんと再婚し、きくさんの娘ゆき子さんを 認知している。ゆき子さんにもお会いしたが、ゆき子さんは「自分は春吉さんの子供で はない」と話した。事情は定かではないが、彼なりの選択であったのだろう。 |
|
小林春吉は戦後をジャーナリストとしてではなく、実業家として歩んだ。 その人脈は幅広いものだった。 春吉を知る銀座の酒屋のご主人は「政治家、右翼、ヤクザとも交際があり、本人も 町の顔役のような感じでもあった」と話してくれた。 銀座七丁目の”お隣りさん”と言うこともあり笹川良一氏とも付き合いあったらし い。 彼の道楽の一つは地域と選挙。銀座界隈の旦那衆で組織する「銀座懇話会」の常任 理事を務め、銀座復興に力を尽くした。 彼はこの組織を保守陣営の選挙運動の母体にしようとした形跡があり、良一さんの 話では、飲み屋で稼いだ金は主として東京都都知事選挙で保守陣営の資金に費やした。 春吉の全貌はいまだはっきりしない。 その中でも分からないのは、天ぷら屋の屋号に「猩猩」という難しい言葉を使った 点である。 広辞苑によると「猩猩」とは「中国の想像上の怪獣で、人に似て体は狗(いぬ)の 如く、声は小児の如く、毛は長く朱紅色で、面貌人に類し、よく人語を解し酒を好む」 とある。 オランウータンのこと、という説もある。 彼が目ざしたのは、反権力で、酒好きで、世話好きで、豪放磊落な、カッコの悪い オランウータンみたいな想像上の動物だったのかもしれない。 小林春吉は常軌を逸する酒飲みで、一晩にビールの大瓶を2ダースも飲んだ、とい う伝説を残し、成人した新聞記者の僕と会うこともなく、1972年4月15日午後4 時、他界した。 それから28年後、僕は第二次世界大戦とともに消滅した「日本魁新聞社」をホー ムページの形で再興しよう、と決意した。 それは一度として会うことが出来なかった亡父・小林春吉に対する思慕の念である。 と同時に、昭和10年代、小林春吉ら巷の言論人が大切にした「自由な言論」「断 固たる言論」が姿を消している”哀しさ”に起因している。 「言葉狩り」が横行し、マスコミが意味のない自己規制を繰り返し「本当のこと」 を書かなくなった。 権力をあざ笑うことはあっても、自らの言論に責任を持たぬメディア。 権力をあざ笑いながら、権力の手先になって世論誘導するメディア。 メディアに働く人は勤勉で、善意に満ちあふれているが、結果的に「本音」を報 道することなく、時代の流れを漫然と傍観する。 それでいいのいだろうか。 僕は、亡父が目指した「言論の自由」を大切にしたいと思い、ホームページという 表現スタイルを選んだ。 自由に書く人間がいて、自由に読む人がいて、誰でもが議論に参加し、去っていく。 ホームページのコストは懐に合わせれば良い。 清貧のままで「言論の自由」を堅持することが可能だ。 2000年7月7日、僕はささやかなホームページを立ち上げ「2代目・日本魁新 聞社」と名付けた。 「二代目魁」のキーワード、それは小林春吉が追い求めた「自由」であり「先駈け」 である。 僕も「自由」を追い求め「魁」を目指す。 小林春吉は富士山を望める「富士霊園」に眠っている。
|